犬のよだれが急にポタポタと垂れ始めた――そんな異変に気づいて、思わずインターネットで検索した方も多いのではないでしょうか。普段は元気で食欲もある愛犬に、突然見られたよだれの増加。原因がわからず不安を感じている飼い主の方は少なくありません。
実は、犬のよだれが急に増える背景には、生理的な反応から病気のサインまで、さまざまな理由が潜んでいます。症状の出方やよだれの性質によって、考えられる原因も異なり、時には緊急性の高いケースもあります。また、ストレスや環境の変化、加齢による身体の変化が関係していることもあるため、単純によだれの量だけを見て判断するのは難しいものです。
この記事では、「犬のよだれが急にポタポタと出る」という症状に対して、考えられる原因や症状別のチェックポイント、受診の目安までをわかりやすく解説しています。実際によくある質問や、飼い主が取りがちな対応についても丁寧に触れていますので、初めてこうした症状に直面した方でも安心して読み進めていただけます。
大切な愛犬の体調を守るために、今できることを一緒に確認していきましょう。読み終えるころには、必要な対処や見極めのポイントがきっと見えてくるはずです。
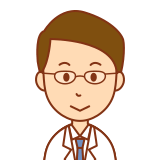
💡記事のポイント
- よだれが急に増える原因の種類と、その見分け方の基本
- 病気のサインとして注意すべきよだれの状態や併発症状
- 日常生活や環境の変化がよだれに与える影響と対応の考え方
- 動物病院を受診すべきタイミングと家庭での観察ポイントの整理
犬のよだれが急にポタポタと出る原因とは?【症状と対処法】

- 犬のよだれが急にポタポタ…知恵袋でよくある質問とは
- 老犬のよだれが急に増えるのは病気のサイン?年齢との関係性
- ストレスが原因?犬のよだれが突然出る心理的要因
- 「元気だけどよだれが多い」場合に考えられる軽度の要因
- よだれがサラサラしている場合と粘ついている場合の違い
- 散歩中に突然よだれが出た…そのとき飼い主がとるべき行動とは
犬のよだれが急にポタポタ…知恵袋でよくある質問とは
犬のよだれが突然ポタポタと垂れるようになったとき、多くの飼い主がまず情報を求めてアクセスするのが「知恵袋」などのQ&Aサイトです。そこでは、同じような経験をした人たちのリアルな声やアドバイスが見られる一方で、情報の正確性には注意が必要です。
知恵袋でよく見かける質問には、「元気はあるけど急によだれが増えた」「食後でもないのにずっとよだれが垂れている」「片側の口からだけよだれが出ている」などがあります。これらのケースでは、多くの飼い主が「異物を飲み込んだのでは?」「口の中にトラブルがあるのかも」と不安を感じている様子が見て取れます。
実際、犬がよだれを多く出す原因はさまざまです。例えば、口の中に小さな傷があったり、歯石がたまっていたりする場合もあります。また、興奮やストレスが一時的によだれを誘発することもあるため、症状だけで判断するのは難しい部分があります。知恵袋では「一晩様子を見るべき」といった回答が散見されますが、状況によってはすぐに動物病院へ行くべきケースもあります。
このような質問サイトの情報は参考程度にとどめ、飼い主自身が冷静に観察を行い、必要であれば専門家の判断を仰ぐことが大切です。過信してしまうと、病気の早期発見を逃してしまうリスクがあるため注意しましょう。
つまり、知恵袋で共有されている体験談は、同じような悩みを持つ飼い主にとって心の支えになる反面、獣医師の診断に勝るものではありません。自分の犬の状態を正しく見極める目を持つことが、もっとも重要な対処法となります。
老犬のよだれが急に増えるのは病気のサイン?年齢との関係性
年齢を重ねた犬に突然よだれの増加が見られた場合、まずは「老化による自然な変化なのか」「何らかの病気のサインなのか」を慎重に見極める必要があります。これを誤って放置すると、進行する病気を見逃してしまう恐れがあります。
老犬になると、体のさまざまな機能が少しずつ低下していきます。特に口腔内のトラブルは増加しやすく、歯周病や口内炎、さらには腫瘍などが原因でよだれが多くなることがあります。こうした変化は、若い犬に比べて進行が遅いために、飼い主が気づきにくい場合もあります。
また、神経系の衰えにより嚥下(えんげ:飲み込む動作)がうまくできなくなり、口の中によだれが溜まりやすくなることも考えられます。とくに口元が垂れてきているような老犬では、よだれが口からこぼれやすくなり、日常的にポタポタと垂れる状態が続くこともあります。
一方で、老犬のよだれが急に多くなった場合には、病気が隠れている可能性も否定できません。例えば、内臓系の疾患や中枢神経系の異常、さらには口の中の腫瘍などが関係しているケースもあるため、軽く考えるべきではありません。特に、食欲の低下や元気がない、嘔吐をともなうなどの症状がある場合は、すぐに動物病院で診察を受けることが推奨されます。
ただ単に「年のせいかな」と思って様子を見てしまうことが、結果として犬の健康を損なうことにもなりかねません。普段の様子との違いに気づくためにも、日頃から愛犬の行動をよく観察しておくことが大切です。
このように考えると、老犬によだれの変化が見られた場合には、老化と病気のどちらの可能性も視野に入れた冷静な判断が求められます。そして何より、少しでも異変を感じたら、早めの受診が安心につながります。
ストレスが原因?犬のよだれが突然出る心理的要因

犬のよだれが突然増えると、飼い主は体の異常を疑いがちですが、実は「ストレス」が影響していることも少なくありません。犬は環境の変化や刺激にとても敏感な動物で、心理的な緊張や不安が体に症状として現れることがあります。よだれの増加もその一つです。
例えば、引っ越しや新しい家族が加わったといった生活環境の変化は、犬にとって大きなストレスになります。また、雷の音や花火、来客など日常的な出来事でも犬は強く反応することがあります。そうした場面で、急によだれを垂らすようになるケースが見られます。
このとき、犬は口の中に異常があるわけではなく、緊張によって唾液の分泌が増えてしまう状態です。とくに、車に乗ったときや動物病院へ向かう途中にだけよだれがひどくなるようであれば、それは不安や恐怖心が原因の可能性が高いです。実際に、乗り物酔いが重なると、よだれだけでなく嘔吐の症状が出ることもあります。
こうしたストレス性のよだれは、一時的なものである場合が多いのが特徴です。環境に慣れたり、状況が落ち着いたりすると自然におさまることも多いため、過度に心配する必要はないケースもあります。ただし、長期間続いたり、他の異常行動(無駄吠え・震え・食欲不振など)も見られるようであれば、精神的な負荷が慢性化している可能性があります。
このように、犬の突然のよだれは体の病気ではなく、心の状態からきている場合もあるのです。対応としては、安心できる空間を作ることや、スキンシップの時間を増やすことが効果的です。場合によっては、行動診療を専門とする獣医師に相談するのも選択肢の一つです。
「元気だけどよだれが多い」場合に考えられる軽度の要因
犬が元気に動き回っているのに、よだれだけが多く見られるとき、深刻な病気ではなく、比較的軽度な原因が隠れている場合があります。こうしたケースでは、よだれの状態や発生したシチュエーションを丁寧に確認することで、問題の特定がしやすくなります。
まず考えられるのが、食べ物に対する期待感です。犬は食事の匂いやおやつの気配を感じると、条件反射的に唾液が分泌されます。これは自然な反応であり、特にフードの準備中やおいしい匂いがする環境では、ポタポタとよだれを垂らすことも珍しくありません。
他にも、暑さや運動後による口呼吸の影響で、よだれが増えることがあります。体温調節のために口を開けてハアハアしていると、唾液が溜まりやすくなり、流れ落ちることがあります。これらはいずれも一過性のものであり、時間が経てば自然と収まることが多いです。
また、前述の通り、ストレスや緊張が一時的に唾液の分泌を促すこともありますが、犬がそれでも普段どおりに遊び、食欲もあり、排泄も問題ない場合には、深刻な問題である可能性は低いと考えられます。
ただし、軽度とはいえ、よだれの質に変化が見られるときは注意が必要です。水っぽいものから泡状、粘り気の強いものへと変化していく場合には、口内の異常が進行している兆候であることもあります。
このため、元気であっても「いつもと違う」と感じたら、症状の頻度や状況をメモしておくとよいでしょう。そうすることで、もし今後動物病院を受診する際にも、正確な情報提供ができ、早期発見につながる可能性が高まります。
つまり、元気な犬によだれが多く見られるときは、必ずしも病気とは限らず、生活の中にある些細な要因が影響していることが多いということです。しかし油断せず、日々の変化に目を配ることが大切です。
よだれがサラサラしている場合と粘ついている場合の違い

犬のよだれには性状の違いがあり、「サラサラしている」ものと「粘ついている」ものとでは、考えられる原因や緊急性が異なります。よだれの変化は口腔内や体の異常を知らせるサインであることもあるため、飼い主としては見逃さずに観察することが大切です。
まず、サラサラとしたよだれは、比較的生理的な分泌であるケースが多い傾向にあります。食事前の興奮や暑さによる体温調節、または緊張やストレスなど、日常的な場面でよく見られます。例えば、フードの準備中に匂いを感じて唾液が出るのは自然な反応ですし、車に乗る前に不安からよだれが増えることもあります。このようなサラサラしたよだれは、一時的であることが多く、犬が元気で食欲もあるようであれば、大きな心配はいりません。
一方で、粘つきのあるよだれが見られる場合は、注意が必要です。このような粘度の高いよだれは、口腔内の炎症や病気、あるいは内臓に何らかのトラブルが生じている可能性を示唆しています。例えば、歯周病や歯のぐらつき、口内炎などによって、口の中に慢性的な刺激が加わると、粘度の高い唾液が分泌されることがあります。また、胃腸の不調や中毒症状でも、粘りのあるよだれが出ることがあり、嘔吐を伴うケースでは緊急の受診が必要です。
このように、よだれの「質」を見極めることは、犬の健康状態を知る手がかりとなります。普段から口元を観察する習慣を持っておくことで、小さな異変にも気づきやすくなります。もし、いつもと違う様子が続いたり、粘ついたよだれに加えて元気のなさや食欲不振が見られたりする場合には、早めに動物病院で診てもらうことをおすすめします。
散歩中に突然よだれが出た…そのとき飼い主がとるべき行動とは
散歩中に愛犬の口から突然よだれが垂れ始めると、多くの飼い主は驚き、どう対応すれば良いのか迷ってしまうかもしれません。このような場面では、まず冷静に犬の様子を観察し、状況に応じた対応を取ることが重要です。
犬が散歩中によだれを出す原因にはいくつかの可能性があります。一時的な興奮や緊張、気温の上昇による体温調節、あるいは路上に落ちている異物を口に入れてしまったことなどが考えられます。例えば、地面に落ちた食べ物の破片や小石を口にしたことによって、違和感を覚え、唾液が増えるということは十分にあり得ます。
このような場合、まず犬の口元を安全な場所で確認してください。可能であれば、水で口をゆすがせたり、異物が見えていれば無理のない範囲で取り除いたりする対応が取れます。ただし、犬が嫌がったり、抵抗を示す場合は無理に触れず、帰宅後に落ち着いた状態で口腔内を確認するか、必要に応じて動物病院を受診してください。
また、散歩中の草や植物、除草剤などをなめた可能性がある場合には、中毒症状を警戒する必要があります。特に、よだれの量が異常に多かったり、嘔吐や震え、呼吸の異常が見られるようであれば、迷わず緊急で病院に連れて行くべきです。そうしたときには、可能であれば犬が接触したと思われる植物や場所の情報を獣医に伝えると、診断の手助けになります。
こうした事態を未然に防ぐためには、散歩中の拾い食いや口に入れる行動をしっかりと制御するしつけが必要です。また、猛暑の日や強い日差しのもとでの散歩は、熱中症のリスクも伴います。水分補給をこまめに行い、なるべく涼しい時間帯に散歩するなどの工夫も大切です。
このように、散歩中の突然のよだれは、さまざまな要因が絡んで起こる可能性があります。その場での犬の様子をよく見て、状況に応じた柔軟な対応を心がけることが、愛犬の健康を守るために重要です。
急によだれがポタポタ止まらない犬への対処法と注意点

- 片側だけよだれが出るときに疑うべき病気とは
- よだれが止まらない…水っぽい・泡状・粘り気のあるケースの違い
- よだれと嘔吐を同時にしている場合の緊急度
- ドッグランや車の中でよだれが出る理由と予防法
- 鼻水と同時に出るよだれ…呼吸器疾患との関連性
- 犬のよだれの主な原因を症状別に解説【獣医師監修情報を元に】
片側だけよだれが出るときに疑うべき病気とは
犬のよだれが片側の口からだけ出ているのを見つけた場合、何らかの体の異常が関係している可能性を考える必要があります。両側から均等によだれが出るのは生理的な反応であることが多いのに対して、片側だけに偏っている場合は、特定部位に問題があるサインとして捉えた方がよいでしょう。
このような状態でまず疑われるのは、口腔内の局所的なトラブルです。例えば、歯の根元に膿が溜まる「歯根膿瘍」や、歯周病による腫れが片側の頬や歯ぐきに起こっている場合、よだれはその炎症箇所側から多く分泌される傾向にあります。さらに、頬の内側を傷つけてしまったり、異物(木の破片や硬いおやつの破片など)が挟まっていたりすることでも、片側だけに唾液が溜まりやすくなるのです。
また、神経の麻痺や顔面の筋肉に関する異常も原因となることがあります。顔面神経が一部麻痺していると、片方の口元の筋肉がゆるみ、唾液を上手く飲み込めなくなることで、垂れてしまうケースも見られます。このような場合は、表情の左右差や瞬きの頻度にも違いが出ることがあるため、併せて観察すると判断の助けになります。
さらに、口腔内にできた腫瘍も見逃してはいけない要因の一つです。良性・悪性を問わず、腫瘍によって一方の口内に違和感や痛みが生じ、犬が無意識によだれを出しやすくなることがあります。痛みが強い場合には、片側だけ頭を傾ける、口を開けたがらないといった仕草も見られることがあります。
このように、よだれが片側からだけ出る場合には、単なる体調の波ではなく、部分的な病気や異常が隠れている可能性が高いです。日を追って症状が続く、食欲が落ちる、顔のバランスがおかしいといった変化が見られた場合は、早めに動物病院で検査を受けることが大切です。
よだれが止まらない…水っぽい・泡状・粘り気のあるケースの違い
犬のよだれが止まらず続いているとき、まず注目すべきなのはその「質感」です。見た目は些細な違いに感じられるかもしれませんが、水っぽい・泡状・粘り気があるなど、それぞれで体内の状態や病気の可能性が大きく異なるため、見逃せない観察ポイントとなります。
水のようにさらっとしたよだれが多量に出ている場合、比較的軽い原因であることが多いです。例えば、食べ物の匂いによる刺激や一時的な緊張など、体が生理的に反応して唾液を出しているケースが当てはまります。ただし、これが長時間続くようであれば、胃のむかつきや軽い吐き気など、内臓に関連した違和感の可能性もあります。犬が頻繁に口をくちゃくちゃ動かしていたり、吐きそうなそぶりを見せたりするならば、消化器の異常を疑う余地があります。
一方で、よだれが泡のようになっている場合は、何らかの刺激や異常な反応が口腔内で起きているサインです。口の中に痛みや炎症がある場合、犬は違和感を解消しようとして舌を多く動かすため、空気を含んで泡状になりやすくなります。また、毒物やアレルギー反応、薬品の誤飲といった中毒症状の初期にも泡状のよだれが現れることがあり、注意が必要です。泡が持続的に出る場合はすぐに動物病院を受診しましょう。
さらに、ねばついた粘度の高いよだれが出る場合には、より深刻な状態が隠れていることがあります。歯周病や口内炎の進行、または口腔内の腫瘍などにより、唾液腺や周囲の組織に異常が生じている可能性があります。このようなよだれは、独特の臭いを伴っていることもあり、犬の食欲が落ちていたり、よだれを垂らすのを嫌がる様子が見られることもあります。
このように、よだれの状態は犬の健康状態を映す「鏡」のような存在です。単なる唾液の量だけでなく、質やにおい、出るタイミングまで含めて観察することが、問題の早期発見につながります。何かいつもと違うと感じたときは、迷わず専門の医師に相談する姿勢が大切です。
よだれと嘔吐を同時にしている場合の緊急度

犬がよだれを流しながら嘔吐しているのを見たとき、飼い主としては非常に不安になります。この2つの症状が同時に起こる場合、犬の体の中で何かしら深刻な問題が進行している可能性があるため、軽視せずに対応することが求められます。
よだれと嘔吐が一緒に見られるとき、まず確認すべきなのは症状が「一時的」なのか、それとも「繰り返されているか」です。例えば、食べすぎや消化不良が原因の場合には、一度の嘔吐で症状が落ち着くこともあります。このときのよだれは、水っぽくさらりとしたものが多く、吐いた後にケロッとしている様子であれば、比較的心配はいりません。
しかし、頻繁に嘔吐を繰り返していたり、よだれが粘ついていて止まらないような状態であれば、体内に異常があるサインと考えた方がよいでしょう。たとえば、胃捻転(胃がねじれてしまう症状)や中毒、膵炎、腸閉塞などの内臓疾患が考えられます。これらは進行が早く、対応が遅れると命に関わることもあります。特に、腹部を触られるのを嫌がる、落ち着きなく動き回る、ぐったりして動かないといった行動が見られる場合は、すぐに病院に連れて行くべきです。
また、誤飲・誤食も見逃せない要因です。人間の食べ物や家庭用品(洗剤・チョコレート・タマネギなど)を口にしてしまった場合、中毒症状としてよだれや嘔吐が現れることがあります。とくに、吐いた物に異物や血が混じっているようであれば、緊急性が高いと判断できます。
このような状況では、症状が出たときの状況をできるだけ詳しく記録しておくことが役立ちます。いつ、何を食べたか、どんな様子だったかを正確に伝えることで、獣医師の判断がスムーズになります。
つまり、よだれと嘔吐が同時に見られる場合、体調の一時的な乱れから命に関わる病気まで幅広い原因が考えられるため、「ただの嘔吐」と軽く見ることなく、犬の様子を丁寧に観察し、必要があれば迷わず医療機関を受診することが大切です。
ドッグランや車の中でよだれが出る理由と予防法
ドッグランや車の中といった特定の環境で、犬が急によだれを垂らし始めることがあります。このような場面におけるよだれの原因は、病気というよりも「外的な刺激や心理的な影響」であることが多く、日常的な対策で十分に予防できるケースも多く見られます。
まず、ドッグランでのよだれについて考えてみましょう。ここでは多くの犬や人と接することになり、特に社交性が高くない犬にとっては、強い緊張や不安を感じやすい場面です。こうしたストレスが引き金となって、唾液の分泌が一時的に増加することがあります。また、走り回ることで体温が上昇し、パンティング(口を開けてハアハアする呼吸)によってよだれが口元から垂れやすくなることも考えられます。
一方、車の中でのよだれは「乗り物酔い」によるものが多く見られます。車の揺れやスピード感、匂いなどが犬にとって大きな刺激となり、平衡感覚が乱れることで胃の不快感が起こります。このときに、嘔吐の前兆としてよだれが大量に出るという反応がよく見られます。犬によっては毎回車に乗るたびに同じ反応をすることもあり、これは一種の条件反射のようになっている場合もあります。
こうした場面での予防法としては、まずは環境に慣れさせることが基本です。ドッグランに行く前に周囲を散歩してから中に入る、他の犬と無理に接触させないようにするなど、少しずつ場慣れさせることでストレスを軽減できます。また、車酔いを予防するためには、乗車前に空腹を避け、こまめな休憩を取りつつ、換気や車内の匂いに配慮することが効果的です。場合によっては、獣医師から酔い止めの処方を受けることも選択肢となります。
このように、ドッグランや車内でのよだれは、外的刺激や心理状態の影響によるものが多く、犬の体調や感受性によっても大きく変わってきます。無理をさせず、犬が安心できる環境を整えることで、多くの場合は改善が期待できます。飼い主が状況を理解し、適切にサポートしてあげることが何よりも大切です。
鼻水と同時に出るよだれ…呼吸器疾患との関連性

犬のよだれに加えて鼻水が出ている場合、それは単なる一時的な症状ではなく、呼吸器系に何らかの異常が起きている可能性を示していることがあります。とくに、よだれが急に増えただけでなく、鼻水が水っぽい、粘り気がある、黄色や緑色をしているなどの場合には、感染症や慢性疾患を疑う必要があります。
呼吸器疾患の中でも比較的多いのが、「犬風邪」とも呼ばれるケンネルコフです。これは複数のウイルスや細菌が関与する感染症で、くしゃみ、咳、鼻水、そしてよだれが組み合わさって現れることがあります。発症初期は軽度な症状に見えることが多く、飼い主としては見過ごしてしまいがちですが、免疫力が落ちている犬や高齢犬では重症化するリスクもあります。
また、慢性的な鼻炎や副鼻腔炎などでも、鼻水とよだれが同時に出ることがあります。これらは鼻の奥に炎症が広がることによって呼吸がしづらくなり、口呼吸が増えることで唾液が溜まりやすくなります。特に寝起きや運動後に症状が強くなる傾向があり、鼻が詰まっていたり、いびきのような音を立てて呼吸する場合には注意が必要です。
他にも、異物(草の種、砂、毛など)が鼻腔内に入り込んで炎症を起こし、それが原因で鼻水やよだれが出ることもあります。こうした場合、片側だけ鼻水が出ることが多く、鼻をしきりにこすったり、くしゃみを頻繁にするなどの行動が見られます。
いずれにしても、鼻水とよだれの組み合わせが長引くようであれば、自己判断で様子を見るのではなく、動物病院で検査を受けることが大切です。レントゲンや血液検査によって、呼吸器の状態や感染の有無が明確になります。早期発見・早期治療が、重症化を防ぐための基本となります。
鼻と口はつながっているため、どちらか一方の異常がもう一方にも影響することはよくあります。このため、鼻水とよだれが同時に現れたときは、それぞれの症状だけでなく、犬全体の体調や行動を総合的に見ることが重要です。
犬のよだれの主な原因を症状別に解説【獣医師監修情報を元に】
犬のよだれにはさまざまな原因があり、その状態や伴う症状によって判断すべきことが異なります。よだれは唾液の一種であるため、自然な分泌そのものは正常な生理反応ですが、量や質、出るタイミングに異常があるときには何らかの健康問題を示している可能性があります。ここでは、よだれのタイプ別に主な原因を整理していきます。
まず、「水っぽくサラサラしたよだれ」が出ている場合、もっとも多いのが興奮や食欲による生理的な反応です。食事の匂いや、遊んでいる最中のテンションの高まりによって、一時的に唾液が増えることがあります。これは元気な犬に見られる自然な反応で、症状が短時間で収まるようであれば心配はいりません。
一方、「泡状のよだれ」が出ている場合は、口腔内に何らかの異常があるか、胃や喉に不快感があることが疑われます。歯周病や口内炎の初期段階では、犬が違和感を紛らわせるように舌を動かすことで、空気を巻き込みながら唾液を泡立てることがあります。また、軽度の胃もたれや吐き気によっても同様の症状が現れることがあります。
「粘り気の強いよだれ」は、より進行した口腔疾患や、唾液腺そのものに異常がある場合に見られます。とくに、歯石の蓄積や歯周病が進んでいる犬では、口臭を伴いながらネバネバしたよだれが常に垂れているような状態になることがあります。このようなときは、口を開けて確認しようとしても痛みのために抵抗を示すことが多いため、無理に触れず、動物病院での診察をおすすめします。
さらに、「よだれと嘔吐がセットで現れる」場合には、消化器系の疾患や中毒、胃捻転などを視野に入れる必要があります。このときは、よだれの質よりも、頻度や他の症状(ぐったりしている、食欲がないなど)に注目してください。
なお、「片側からのみよだれが出る」場合には、前述の通り、口内の局所的な問題(歯の根の膿や口内腫瘍など)が原因となっていることがあります。これは明らかに異常な状態なので、早急な診察が必要です。
このように、よだれの状態や出方にはそれぞれ意味があり、症状を正しく見分けることが早期発見・早期治療のカギとなります。日頃から犬の様子をよく観察し、少しでも「いつもと違う」と感じたら、獣医師に相談するよう心がけましょう。それが、愛犬の健康を守るためにできるもっとも確実な方法です。
犬のよだれが急にポタポタ出るときに知っておきたい症状と対処のまとめ

- Q&Aサイトでは「元気なのによだれが出る」といった相談が目立ち、飼い主の不安が多い状況がうかがえる
- 片側だけよだれが出ている場合は、歯や口内の局所的な病変が原因であることが多く、早めの診察が望ましい
- 老犬のよだれ増加は、歯周病や飲み込む力の衰えといった加齢変化による可能性が高い
- 環境の変化や来客、音への反応などストレスが唾液分泌を促すことがあり、心因性のケースも想定される
- 車やドッグランなど新しい場所に行った際、緊張から一時的によだれが増えることがあるため、慣れる時間が必要
- 食べ物の匂いやごはんの時間に反応して出るよだれは、生理的なものと考えて問題ない
- 暑さや運動で体温が上がり、ハアハアと口呼吸することで唾液があふれることがある
- 水のようにサラサラしたよだれは軽い消化不良や緊張時にも起こりやすく、経過観察で済むケースが多い
- 泡状のよだれは、口内炎や歯の痛み、中毒などの異常反応によって引き起こされることがある
- 粘り気のあるよだれは、進行した歯周病や腫瘍のような慢性的な疾患が隠れている場合がある
- 嘔吐を伴うよだれは、胃捻転や中毒など緊急対応が必要な内臓疾患のサインであることもある
- 鼻水とよだれが同時に出る場合は、呼吸器感染や副鼻腔炎、鼻腔内異物などの疾患が疑われる
- 散歩中に落ちているものを口にして異物を飲み込んだことが、よだれの急な増加につながることがある
- よだれの状態が続く、あるいは他の症状も伴う場合は、迷わず動物病院を受診した方が安心できる
- 症状が出た時刻や状況を記録しておくと、診察時に正確な情報提供ができ、診断の助けになる
関連記事



コメント