山や田舎道を歩いていると、ふと足元に現れるマムシ。その危険性から敬遠されがちな存在ですが、実は「捕まえて売るとお金になる」と聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。特にネット上では「マムシの捕まえ方」や「売ると儲かる」といった情報が話題になり、興味を持つ人が増えています。
この記事では、マムシを捕まえることは本当に可能なのか、また、捕まえたマムシを合法的かつ安全に売るには何が必要なのかを、初心者にもわかりやすく解説していきます。生息地や出現する時間帯の傾向、安全な見分け方、咬まれた際の対処法、さらには売買に関する法律や許可についても網羅的に取り上げています。
「危険だけど、きちんと知っておきたい」「合法的に取り組みたい」「安全に売る方法を知りたい」そんな方に向けて、この記事は信頼できる情報を丁寧にお届けします。マムシをただの脅威として避けるのではなく、正しく理解することが、自分と周囲を守る第一歩になるはずです。
読み終わる頃には、あなたもマムシに対する見方が少し変わっているかもしれません。どうぞ最後までお付き合いください。
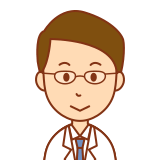
- マムシを捕まえる際の法律や安全面での注意点
- マムシが出現しやすい場所や時間帯の特徴
- 捕獲したマムシの販売方法と市場価格の目安
- 売買を行うために必要な許可や手続きの内容
マムシの捕まえ方と売るための注意点

- マムシを捕まえてもいいですか?
- マムシが出現しやすい場所は?
- マムシの活動時間と危ない時期
- マムシの模様と特徴で見分ける
- マムシの尻尾を振る行動の意味とは?
- マムシの致死率と対処法
マムシを捕まえてもいいですか?
結論から言うと、マムシを捕まえること自体は「完全に禁止されているわけではありません」が、地域によっては法的な規制や制限があるため、事前に確認が必要です。具体的には、マムシは一部の自治体で保護対象となっている場合があり、捕獲や売買に許可が必要なケースもあります。また、自然公園や保護区域などでは、動植物の捕獲が全面的に禁止されていることもあるため、場所によって状況が異なります。
このため、無許可での捕獲が違法行為とされる可能性もあるのです。たとえマムシを個人で利用したい、あるいは販売目的であっても、事前に都道府県の環境保護課や自然保護センターに問い合わせることを強くおすすめします。さらに、鳥獣保護管理法の観点からも、ヘビ類の扱いには注意が必要です。
例えば、ある県では生きたマムシを捕まえて販売するために、特定の狩猟免許と動物取扱業の届け出が必要とされています。この手続きがなされていない場合、法的責任を問われることになりかねません。
そしてもう一つは、安全面での懸念です。マムシは毒蛇であり、咬まれると命に関わる可能性もあります。経験や知識がないまま捕獲を試みるのは非常に危険であり、自己判断での行動は控えるべきでしょう。仮に捕獲が合法だったとしても、安全管理や応急処置の知識がないまま行うのは無謀です。
このように、マムシを捕まえることには法的・安全的なリスクが伴います。安易に「売れるから」「珍しいから」と行動するのではなく、まずはしっかりと情報を集め、必要な許可を得た上で慎重に対応することが大切です。
マムシが出現しやすい場所は?
マムシは日本の多くの地域に生息しており、その出現場所には一定の傾向があります。特に湿度が高く、草木が生い茂っているような場所に現れることが多いです。例えば、山林のふもと、田んぼのあぜ道、河川敷、用水路の近くなどが典型的な生息地として知られています。
このような場所では小動物やカエルなど、マムシのエサとなる生き物も豊富に存在します。マムシはそれらを狙って潜んでいるため、人が気づかずに近づいてしまうことがあります。また、石垣の隙間や落ち葉の積もった場所、古い木材の下など、身を隠せるスペースがある場所も好まれる傾向があります。
私の場合、過去に田舎の農村地帯で何度かマムシを目にしたことがありますが、いずれも水辺の近くで、足元に注意していなければ見逃してしまいそうな場所でした。このような環境では、マムシはじっとしていることが多く、気づかずに近づくと突然咬まれる危険もあるため注意が必要です。
また、季節や時間帯にも出現の傾向があります。特に初夏から秋にかけての暖かい時期、そして朝夕の時間帯は活動が活発になるとされています。これは外気温がマムシの体温調整に適しているためであり、逆に真夏の昼間などは暑さを避けて物陰に潜んでいることが多くなります。
ここで一つ注意すべき点があります。それは、「人里から離れていれば安心」とは限らないということです。実際には、住宅地の近くでも河川敷や竹林、放置された空き地などがあればマムシは出没する可能性があります。特に近年は、里山の開発や自然環境の変化により、マムシの生息域が人間の生活圏と重なるケースも増えています。
このように考えると、マムシは意外と身近な場所に潜んでいる可能性があるため、自然の多い地域を歩く際は十分な注意が必要です。草むらに手を入れる、無防備に座り込むといった行為は控えるよう心がけましょう。
マムシの活動時間と危ない時期
マムシは一年を通して見られるわけではなく、活動する時期や時間帯には特徴があります。これを理解しておくことで、遭遇リスクを減らすことが可能になります。特に自然の中で作業をする方や、子どもを連れて散策する人にとっては重要な知識です。
まず、マムシが活発になるのは春から秋にかけての暖かい季節です。具体的には4月中旬頃から活動を始め、10月頃までその姿を見かけることがあります。この間は気温が上がることで体温が上がりやすくなり、エサを求めて行動範囲が広がります。
また、1日の中で活動する時間帯にも傾向があります。多くは朝方と夕方、つまり気温が穏やかな時間帯に動く傾向があります。真夏の昼間のように暑すぎる時間帯は、直射日光を避けて日陰や草むらに潜んでいることが多いため、むしろその時間帯に不用意に草の中に手を入れることのほうが危険と言えるかもしれません。
一方で、春先や秋の気温が下がり始めた時期には、日光を浴びて体温を上げようと、開けた場所に姿を現すことがあります。つまり、春と秋の晴れた日中は特に注意が必要です。見通しの良い場所でも、岩の上やアスファルトの道路でとぐろを巻いていることがあるため、うっかり踏んでしまう危険があります。
そしてもう一つ、注意すべきなのは「繁殖期」です。マムシは夏(6月~8月頃)に交尾を行い、晩夏から初秋にかけて出産します。この時期は警戒心が強くなり、攻撃的な行動を見せる個体も増える傾向があります。特にメスは子を守る本能から、普段よりも反応が素早くなることがあります。
このような背景を知っておくことで、どの季節・どの時間帯に注意を払うべきかが明確になります。山林や農作業を行う方、またはハイキングなどの自然活動をする方は、春から秋の朝夕を中心に、足元や手を入れる場所への警戒を怠らないよう心がけましょう。
マムシの模様と特徴で見分ける

マムシは日本国内で比較的よく見られる毒蛇ですが、見た目の特徴を理解していないと他の無毒なヘビと見分けがつかない場合があります。マムシは攻撃性が強いわけではありませんが、見分けられずに近づいてしまえば咬まれるリスクが高まります。そのため、安全な距離を保つためにも、模様や体の特徴を正確に知っておくことが大切です。
まず最も目立つ特徴として、**体に沿って並ぶ銭型模様(楕円形やひし形に見える模様)**があります。これが体の左右に交互に配置されており、上から見ると波のように見えることがあります。この模様は成体・幼体問わずほとんどの個体に見られるため、最も信頼できる見分け方の一つです。
また、頭部の形にも注目すべきポイントがあります。マムシは頭が三角形に近く、首がくびれているのが特徴です。これは毒腺が発達しているためであり、他のヘビに比べて頭部の存在感が際立っています。さらに、目の形も見分けの手がかりになります。マムシの瞳孔は縦に細長いスリット状で、猫の目のように見えることが特徴です。
一方で、よく間違えられるヘビとして「アオダイショウ」や「シマヘビ」がいます。これらは無毒ですが、模様が似ている部分もあるため注意が必要です。例えば、若いシマヘビは茶色い体に模様があり、遠目にはマムシと見間違えることがあります。ただし、頭の形が丸みを帯びていたり、瞳孔が丸かったりする点で違いが見られます。
また、幼体のマムシには「赤い尻尾」があるという特徴があります。この尻尾を使ってエサとなる小動物をおびき寄せる行動が見られるため、山や田んぼで小さな赤い尻尾のヘビを見かけた場合も注意が必要です。
このように、模様・頭の形・瞳孔の形・幼体の尻尾といった複数の特徴を組み合わせて判断することで、マムシを正確に見分けることが可能になります。見た目だけで完全に判断するのは難しい場面もありますが、少なくとも危険性を感じた場合は無理に近づかず、その場を離れる行動を心がけてください。
マムシの尻尾を振る行動の意味とは?
マムシが尻尾を振る動作には、明確な意味と目的があります。これは単なる癖や偶然の動きではなく、身を守るための威嚇行動の一種と考えられています。自然界では、体の動きや音を使って敵に自分の存在を知らせたり、逆に遠ざけたりする動物が多く見られますが、マムシもその一例です。
この行動が特に顕著に見られるのは、外敵に接近されたときや、驚いたときです。尻尾を細かく震わせたり、地面をこすったりすることで「シャッ、シャッ」というようなかすかな音を発する場合があります。この音自体はそれほど大きくはないものの、小動物や人間に対して警告として機能します。つまり、「これ以上近づくな」というサインなのです。
私が過去に遭遇した事例でも、草むらの中で不自然な音が聞こえた直後に、マムシがとぐろを巻いて身構えているのを見つけたことがあります。そのとき、音に気づかずに足を踏み出していれば、咬まれていた可能性もあったでしょう。このように、マムシの尻尾を振る行動は、自衛のための重要なサインであり、無視してはいけません。
また、幼体のマムシには異なる意味を持つ行動もあります。赤やオレンジ色の目立つ尻尾をゆっくりと動かすことで、小動物を引き寄せる「ルアー行動」と呼ばれる捕食手段を使うことがあります。これは威嚇ではなく、むしろエサをおびき寄せるためのものです。つまり、同じ「尻尾を振る」という行動でも、成体と幼体では目的が異なる場合があるということです。
こうして見ていくと、マムシの尻尾の動きには複数の意味が込められていることがわかります。野外でこのような動きを見かけた場合は、不用意に近づかず、その場を静かに離れるようにしてください。音に気づくことが、自分の命を守る第一歩となるかもしれません。
マムシの致死率と対処法
マムシは日本に生息する毒蛇の中でも、特に人との遭遇率が高い種類です。そのため、咬まれるリスクも現実的に存在しますが、「咬まれたらすぐに死ぬ」という印象は、正確とは言えません。実際、マムシに咬まれた際の致死率は非常に低く、数パーセント未満とされています。しかし、それは適切な処置が行われた場合の話であり、決して軽視してよい問題ではありません。
マムシの毒は、主に出血毒と細胞毒で構成されており、咬まれると激しい腫れや痛み、吐き気、発熱などの症状が出ることがあります。場合によっては筋肉の壊死や全身性のショック症状を引き起こすこともあり、高齢者や子ども、持病のある人にとっては命に関わることもあるため油断は禁物です。
では、万が一咬まれてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。まず、絶対にやってはいけないのが、毒を吸い出そうとすることです。古い知識では「口で毒を吸って吐き出す」という方法が紹介されていましたが、これは感染症のリスクや逆に毒の広がりを促進してしまう危険があるため、現在は推奨されていません。
正しい対応としては、まず患部を心臓より低い位置に保ち、安静にして動かさないことが重要です。毒が全身にまわるのを遅らせるために、無理に歩いたり走ったりしてはいけません。そのうえで、できるだけ早く病院へ向かうことが何よりも大切です。医療機関では、必要に応じて抗マムシ毒血清が投与されることがありますが、これは副作用のリスクもあるため医師の判断で慎重に使用されます。
なお、咬まれた直後に明確な症状が出ない場合でも、油断はできません。症状が数時間後に現れるケースもあるため、咬まれた形跡があれば必ず医療機関を受診しましょう。
このように、マムシの咬傷は命に関わる重大な事態にもなりかねませんが、冷静に対応すれば致命的な結果を避けられる可能性は高くなります。自然の中で行動する際は、万が一の事態に備えて応急処置の知識を身につけておくことが重要です。そして何より、遭遇しないよう注意深く行動することが、最も有効な予防策と言えるでしょう。
捕まえたマムシは売れるのか?

- 生きたマムシの値段は?
- マムシでお金稼ぐ方法とは?
- マムシの寿命と取り扱い
- マムシ退治との違い【捕獲と駆除の使い分け】
- マムシ退治方法とその是非
- マムシを安全に売買するには?
生きたマムシの値段は?
生きたマムシの価格は、取引されるルートや需要、捕獲された地域によって大きく異なります。一般的に言われている相場では、1匹あたり2,000円〜5,000円程度で売買されることが多いようです。ただし、これが常に保証されているわけではなく、買い手が見つかるかどうかや、法的な制約の影響も受けるため、実際の収益につながるかは慎重に見極める必要があります。
主な需要先としては、漢方薬の原料や滋養強壮の酒(いわゆるマムシ酒)に使用する業者、研究機関、または伝統的な薬膳料理を扱う店などが考えられます。特に生きた個体は鮮度が高く、加工用としての価値が上がるため、冷凍された個体よりも高値がつく傾向があります。ですが、それはあくまで取引先が合法かつ正規ルートであることが前提です。
一方で、一般人が自由にマムシを捕まえて売ることには、法律上の規制や許可が関わってくる点に注意が必要です。たとえば、動物愛護管理法や鳥獣保護管理法の対象となる可能性があるため、自治体によっては許可なしに生きたマムシを取り扱うことが禁止されている場合もあります。この点を無視して売買を行った場合、法令違反として罰則が科される恐れもあるため、事前の確認は必須です。
また、マムシの大きさや健康状態によっても値段は変動します。傷がある個体や弱っている個体は値が下がることがあり、逆に健康な個体であれば希望価格に近い額で売れる可能性もあります。ただ単に捕まえるだけではなく、捕獲後の取り扱いや保管方法によっても最終的な価値に差が出るというわけです。
このように、マムシの価格には複数の要因が関与しており、単純に「捕まえれば儲かる」というものではありません。利益を期待するのであれば、取り扱いの知識や販売先の確保、そして法的な手続きについても十分に調べておくことが大切です。
マムシでお金稼ぐ方法とは?
マムシを利用して収入を得る方法はいくつかありますが、どの手段を選ぶにしても「安全性」と「法的な正当性」が不可欠です。闇雲に捕まえて売ろうとする行為は、リスクが大きいだけでなく、法令違反に問われる可能性もあるため、しっかりとした準備と計画が必要になります。
まず一般的なのは、マムシを捕獲して業者へ販売する方法です。主な取引先としては、製薬会社、漢方や民間薬を扱う企業、または食品加工業者などがあります。この場合、生きたまま納品する必要があることも多く、輸送中の管理や取り扱い方法にも専門的な知識が求められます。中には冷凍処理した状態での買取を希望する業者もありますが、それでも衛生面や保管方法に一定の基準が課されるのが一般的です。
次に考えられるのが、マムシ酒の自家製造と販売です。ただし、ここでも注意が必要です。アルコールと毒蛇を使った漬け込み酒は、家庭で作る分には法律上の問題がないとされていますが、それを販売するとなると酒税法や食品衛生法の対象になります。製造・販売許可を取らずに商品化すれば、重大な法的問題に発展しかねません。あくまで自家消費にとどめるのが安全な範囲です。
また、もう一つの方法としては、自然体験や教育イベントでの展示・解説を通じた収益化です。これは比較的安全かつ合法的に行えるケースもあります。例えば、マムシの生態を紹介するセミナーを開催したり、自治体やNPO法人と連携して毒蛇の危険性を啓蒙する活動に携わることで、報酬を得ることができます。この方法であれば、マムシそのものを売るわけではないため、動物取扱業の許可や輸送リスクの心配も比較的少なくて済みます。
ただし、どの方法を選ぶにしてもマムシを扱うには相応の知識と経験が求められることは忘れてはいけません。不用意に扱うと自分自身が咬まれるリスクも高く、安全管理が不十分なままの活動は周囲の人々にも危害を及ぼす可能性があります。初めての方は、まず専門家の指導を受けるか、信頼できる団体と連携することが望ましいでしょう。
このように、マムシで収益を得る道は存在しますが、それを継続的かつ安全に行うためには、多くの準備と責任が伴います。合法性・安全性・市場性の3つを満たしてこそ、初めて「お金を稼ぐ手段」として成り立つのです。
マムシの寿命と取り扱い
マムシの寿命は、自然界ではおおよそ10年程度とされています。もちろん、すべての個体がその年齢まで生きられるわけではなく、多くは捕食や環境変化、病気などによってもっと早い段階で命を落とすこともあります。とはいえ、条件が整えば長く生きる生き物であるため、取り扱いには継続的な管理が求められます。
まず、マムシを取り扱ううえで注意したいのは、「生きたまま保管する場合」と「捕獲後すぐに加工または処理する場合」で必要な対応が大きく異なるという点です。生きたまま一時的に保管する場合は、密閉された通気性のある容器に入れ、逃げ出さないように厳重な管理をする必要があります。ヘビは意外にも力が強く、狭い隙間でも体を押し込んで脱出を試みるため、市販の昆虫ケースなどでは対応しきれないことがあります。
さらに、温度や湿度の管理も重要です。マムシは変温動物なので、環境温度によって活動レベルが変わります。暑すぎる場所では弱ってしまいますし、寒すぎると動きが鈍くなる反面、急な刺激に対して過剰に反応することもあるため危険です。特に屋内での取り扱いを考える場合には、気温管理が行き届く専用の飼育環境を整えなければなりません。
また、食事の世話も簡単ではありません。自然界ではカエルやネズミ、小型の鳥などを捕食していますが、飼育下でこれらを与えるにはエサの確保と衛生管理が必要になります。加えて、咬まれないように世話をするための器具や保護具も欠かせません。
取り扱いのもう一つの注意点は、周囲の人への安全配慮です。たとえ個人的な興味や研究目的であっても、毒蛇を家に置くことは大きな責任を伴います。万が一脱走してしまった場合、近隣住民にとっては命に関わる事故になる可能性もあります。そのため、自治体によってはマムシの飼育や保管に関して届け出や許可が必要とされることもあります。
このように、マムシは長生きする可能性のある生物である一方、取り扱いには高い専門性と責任が求められます。軽い気持ちで飼育や保管を始めることは避け、十分な準備と法的な確認を経て行動するようにしましょう。
マムシ退治との違い【捕獲と駆除の使い分け】

マムシへの対処には大きく分けて「捕獲」と「退治(駆除)」の2つのアプローチがあります。一見似ているようでいて、目的も方法もまったく異なるため、状況に応じた使い分けが求められます。
まず、「捕獲」とはマムシを生きたまま捕まえる行為を指します。これは研究や薬用利用、あるいは販売目的など、対象を殺さずに扱うことを前提としています。捕獲には、専用の器具や知識、安全対策が必要で、咬まれるリスクが高いため、経験者や有資格者が行うことが推奨されます。
一方で、「退治」はマムシをその場で駆除する(殺処分する)行為です。これは主に人命の安全確保や生活環境の保護を目的としています。例えば、住宅の庭先に出現したマムシが人やペットに危険を及ぼす可能性が高い場合、その場で速やかに駆除する選択がとられることがあります。特に、子どもや高齢者が多く出入りするエリアでは、安全を最優先するために退治が適切とされる場合も少なくありません。
ここで注意すべきなのは、どちらの方法にも法的制約があるという点です。マムシは一部の自治体では「特定動物」や「指定管理鳥獣」に分類されており、捕獲・駆除のいずれを行う場合でも許可が必要なことがあります。また、私有地であっても勝手に薬剤や罠を使用して退治することは、他の動物や人に影響を及ぼす恐れがあるため慎重に行うべきです。
実際、野外活動中にマムシと遭遇したとしても、むやみに捕まえたり退治しようとしたりするのではなく、まずは距離を取ってその場を離れるのが最も安全な選択です。そのうえで、必要があれば専門機関や自治体に相談することが望ましい対応となります。
このように、マムシへの対応は目的と状況によって大きく異なります。捕獲が適切な場合もあれば、退治が避けられない場面もあるため、どちらが正しいという単純な話ではありません。大切なのは、人間とマムシの両方の安全を考慮しながら、適切な方法を冷静に選ぶことです。その判断には知識と準備、そして場合によっては専門家の助けが必要になることを理解しておきましょう。
マムシ退治方法とその是非
マムシを退治する方法にはいくつかの手段がありますが、最も重要なのは「人間の安全を確保する」ことです。マムシは毒を持つ危険なヘビであるため、出現した場所や状況によっては退治が必要になるケースもあります。ただし、その是非については慎重に判断する必要があります。
一般的な退治方法として知られているのは、棒や鋤(すき)などの道具を使って直接叩く方法や、殺蛇用の忌避剤や煙、薬剤を使う方法などです。中には、捕獲後に殺処分するケースもあります。こうした方法は、咬まれるリスクが差し迫っている場合や、子どもやペットのいる場所にマムシが現れたときなどには有効とされています。
例えば、家庭の庭や学校の敷地内、キャンプ場など、利用者の多いエリアに出没した場合、マムシを放置することが逆に大きな事故を引き起こす可能性があります。こうしたケースでは、やむを得ず駆除を選択する判断も理解されやすいでしょう。実際、自治体によっては「マムシ駆除手当」などの制度を設けているところもあり、一定の条件下での退治は公的に認められている例もあります。
一方で、安易な退治は避けるべきです。自然界において、マムシも生態系の一部を構成する存在です。ネズミやカエルなどの個体数を調整する役割があり、すべてを無差別に駆除すれば、別の害獣被害が増える可能性もあります。さらに、マムシを退治する行為には鳥獣保護管理法や都道府県の条例が関わってくることもあり、無許可での処分が違法とされるケースもあります。
ここで考えるべきなのは、「本当に退治する必要があるのか」という点です。その場を離れることで安全が確保できるなら、あえて駆除せずに専門業者に依頼したり、自治体へ相談する方が安全かつ合法的です。特に個人での対処には限界があるため、プロに任せる選択肢を持つことも重要です。
このように、マムシ退治には効果的な手段が存在しますが、それを実行するかどうかは周囲の環境や法的制約、そして生態系への配慮を踏まえて判断すべきです。必要な場面では的確に対応しつつも、不必要な殺生を避ける姿勢が、より安全で持続可能な選択と言えるでしょう。
マムシを安全に売買するには?
マムシの売買を行うことは、一定の条件を満たしていれば可能ですが、決して自由に誰でも行えるものではありません。特に毒蛇であるマムシは、安全性や法的制約の観点から、慎重な取り扱いが求められます。適切な手続きや管理を怠れば、法的トラブルや事故につながる恐れがあるため、安易な売買は避けるべきです。
まず最初に確認しておくべきなのが、販売には各種許可が必要であるという点です。たとえば、動物取扱業の届け出は、マムシを生きたまま扱う場合に必要とされる代表的な許可の一つです。さらに、地域によってはマムシが「特定動物」や「準絶滅危惧種」に指定されていることもあり、その場合は捕獲・販売・輸送すべてにわたって規制を受ける可能性があります。売買を検討する際は、まず地元の自治体や保健所に確認を取りましょう。
次に、安全管理の観点からは、輸送中や保管中の管理体制を整えておくことが不可欠です。生きたマムシを移動させる際には、専用のケースや容器を使用し、脱走や咬傷事故を防ぐための対策を施す必要があります。特に公共交通機関を使っての輸送は禁じられている場合が多いため、個別輸送や業者依頼などの方法を検討することになります。
また、販売先の選定にも注意が必要です。医療機関や漢方薬関連の業者など、正規ルートを持つ相手に限定して取引を行うことが重要です。SNSやオークションサイトなどで安易に取引を始めると、違法取引や詐欺の温床になる恐れがあります。相手が免許や許可を持っているか、法的な手続きを経ているかを必ず確認するようにしましょう。
さらに、税務や帳簿管理といったビジネス面でも注意が必要です。個人であっても、継続的にマムシを販売する場合は事業所得として課税対象になる可能性があります。確定申告を行う義務が生じる場合もあるため、必要に応じて税理士など専門家のアドバイスを受けることも検討しておくと安心です。
このように、マムシを安全かつ合法的に売買するには、法令の確認、安全管理、信頼できる取引先の確保など、複数のハードルをクリアする必要があります。短期的な利益を目的に安易に始めるのではなく、しっかりと準備と知識を備えたうえで慎重に行動することが、トラブルを避けるための最善策です。
マムシの捕まえ方と売れるために知っておくべき15のポイント

- マムシの捕獲は、地域によっては条例や法律で厳しく制限されており、場合によっては全面的に禁止されていることもある
- 捕獲を行う前には、各自治体の環境保護課や自然保護センターに確認を取り、必要な許可を取得することが求められる
- 無許可でマムシを捕まえて販売した場合、鳥獣保護管理法や動物愛護管理法などに抵触する恐れがある
- マムシは毒を持つため、素人が知識や装備なしで捕まえようとすると、命に関わる事故を引き起こす可能性がある
- 湿気が多く草木が密集した場所や、田んぼのあぜ道、用水路や河川敷などは、マムシの出現頻度が特に高い
- 春から秋にかけてが活動シーズンであり、気温の穏やかな朝夕に活発に動く傾向が見られる
- 6月から8月にかけての繁殖期は警戒心が強く、メスのマムシは攻撃的になることもあるため、特に注意が必要
- 成体のマムシは体側に銭型の模様があり、三角形の頭部や縦長の瞳孔などの特徴から他のヘビと見分けることができる
- 幼体のマムシは尾の先が赤く、小動物をおびき寄せるために尻尾を動かす「ルアー行動」を取ることがある
- マムシが尻尾を振る行動は、音を立てて敵に警告する威嚇の一種であり、不用意に近づくと咬まれる危険が高まる
- マムシに咬まれても致死率は高くないが、激しい腫れや壊死、ショック症状などの重い症状が出ることがある
- 咬傷を受けた際は、毒を吸い出さずに安静を保ち、速やかに医療機関へ搬送するのが最も安全な対応である
- 生きたマムシは用途や状態によって価格が変動するが、一般的には1匹2,000円から5,000円程度で取引されている
- 取引先には漢方薬業者や食品加工会社などがあるが、販売には動物取扱業の届け出やその他の許可が必要となる
- マムシで安定的に収益を得るには、法令順守を前提に、安全管理・販売ルートの確保・知識の習得が不可欠である
関連記事



コメント