「アライグマはなぜ洗うの?」と気になって検索した方は、おそらくあの愛らしい仕草に目を奪われたのではないでしょうか。前足を水の中でこすり合わせる様子は、まるで人間が手を洗っているかのように見え、SNSや動画サイトなどでもたびたび話題になっています。
しかし、その行動には本当に“洗っている”という意味があるのでしょうか?実は、アライグマのこの仕草には私たちが想像している以上に深い理由と、生き抜くための本能的な戦略が隠れています。さらに、日本におけるアライグマの存在は可愛らしさだけでは語れない、環境や生活への影響も伴っています。
この記事では、アライグマの「洗うような行動」の真相から始まり、名前の由来、わたあめを洗う動画の裏側、そして野生動物としての実態や人への影響まで、多角的に掘り下げてご紹介します。読み進めるうちに、きっと「なぜ洗うのか?」という疑問だけでなく、「なぜ身近な問題になっているのか?」という新たな視点にも気づくはずです。最後までじっくりとお付き合いください。
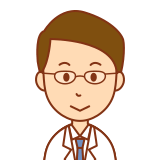
💡記事のポイント
- アライグマの洗うような仕草の本当の意味
- 洗っているように見える行動が生態に基づくものであること
- アライグマが日本に定着した背景と増加による問題点
- アライグマの生態や人間との関わり方
アライグマはなぜ洗う?仕草の理由と本当の意味

- アライグマ 洗う仕草は何のため?
- アライグマは手を洗っているわけではない?
- アライグマ 洗ってるところがかわいいと話題
- アライグマ わたあめを洗う行動の背景とは
- アライグマ 目が悪いことと洗う行動の関係
- アライグマ 名前の由来と“洗う”の関係性
アライグマが洗う仕草は何のため?
アライグマが前足を水の中でこするような仕草を見せることがあります。この行動を見て「手を洗っているみたいで可愛い」と感じた方も多いのではないでしょうか。しかし、アライグマがこのような動きをするのには、明確な意味があります。
実際には、アライグマが水辺で前足を動かす行動は「感触によって周囲のものを把握するため」と考えられています。アライグマの前足には非常に多くの神経が通っており、触覚が非常に発達しています。つまり、物を目で見るのではなく、触れて感じることで情報を得ているのです。
例えば、水中にある食べ物を見つけたり、異物を区別したりするとき、前足でじっくりと確認します。これが、まるで何かを「洗っている」ように見える理由です。特に暗い場所や水が濁っている場所では、視覚よりも触覚に頼る傾向が強くなります。
一方で、この行動が常に水の中で行われるとは限りません。乾いた場所であっても同じような前足の動きをすることが観察されています。つまり、水はあくまでも補助的な要素であり、「洗っている」わけではないのです。
このように、アライグマの洗うような仕草には、獲物を探したり、食べ物の状態を確かめたりするという、野生下で生き抜くための本能的な行動が隠れています。可愛らしいだけでなく、非常に理にかなった行動であることがわかります。
ただし、飼育下のアライグマでもこの行動が見られることがありますが、それは本能的な動きが残っているからです。人間のような「衛生意識」ではなく、生きるための行動という点を理解しておくことが大切です。
アライグマは手を洗っているわけではない?
アライグマが前足を水につけてこすり合わせる仕草は、まるで人間が手を洗っているように見えます。しかし、この行動は衛生のために手をきれいにしているわけではありません。
アライグマのこの行動には、「手を使って物を確認する」という目的があります。前述の通り、アライグマの前足は非常に繊細で、細かいものの形や質感を感じ取る力が強いです。水の中で手を動かすのは、獲物や食べ物の位置を正確に把握するための手段にすぎません。
これを「洗っている」と表現するのは、あくまでも人間側の印象に過ぎません。アライグマは自分の手を清潔に保とうとしているわけではなく、本能的に物の状態を把握する行動を取っているだけなのです。これは、野生下で生きるための工夫といえるでしょう。
例えば、水の中に潜む貝や昆虫を探すとき、視覚に頼るよりも、前足で触って確認する方が正確です。手を使ってこすり合わせるような動きは、まさにその作業の一部なのです。暗所でも同じような動作をすることがあるため、必ずしも水が必要というわけではありません。
また、動物園などの飼育環境でも、アライグマがこのような動きを見せることがありますが、これは野生での習性が残っているためです。つまり、環境にかかわらず行われるこの動作は、アライグマ本来の生態を反映したものなのです。
このように考えると、「アライグマが手を洗っている」という見方は、かわいらしい誤解ともいえるかもしれません。正確には、物を見極め、食べられるかどうかを判断するための本能的な行動です。見た目の印象に惑わされず、その背景にある自然の仕組みに目を向けてみると、より興味深くアライグマを観察することができるでしょう。
アライグマの洗ってるところがかわいいと話題

アライグマが前足を水の中で動かしている姿は、多くの人に「まるで手を洗っているみたい」と言われ、SNSなどでもたびたび話題になります。その仕草があまりにも人間的で、見ているとつい笑ってしまうような可愛らしさがあるためです。実際、「アライグマ 洗ってるところ」といった検索ワードで、動画や画像を探す人も少なくありません。
このような行動が話題になる背景には、私たちがアライグマの仕草を擬人化して捉えやすいという心理も関係しています。人間の赤ちゃんが手をこすり合わせる様子や、水遊びをしているようにも見えるその動きは、親しみやすさを感じさせ、感情移入を誘いやすいものです。加えて、アライグマの丸くて表情豊かな顔立ちや、もこもこした体毛も視覚的な可愛らしさを強調しています。
例えば、動物園の展示やSNSでよく見られるのが、水に入れたエサを前足でまさぐっている様子です。このとき、前足をじっくり動かしながら何かを確認するようにしている姿は、人間の「手洗い動作」に非常に似ており、思わず見入ってしまうことがあります。
ただし、このような「可愛らしい行動」がすべて無害であるとは限りません。野生のアライグマは非常に賢く、環境への適応力も高いため、人家の周囲に現れてゴミを漁ったり、農作物を荒らしたりすることがあります。つまり、見た目のかわいらしさだけで判断するのではなく、野生動物としての側面も理解する必要があります。
こうした点をふまえると、アライグマの洗うような仕草は単なる癒しの対象というだけではなく、その生態や能力を知るきっかけにもなります。映像や画像を楽しむ一方で、アライグマという動物が持つ特性についても意識を向けてみると、より深い理解につながるでしょう。
アライグマがわたあめを洗う行動の背景とは
アライグマがわたあめを水で洗って溶かしてしまう動画は、世界中で話題になりました。この行動は一見ユーモラスに見えますが、実はアライグマの本能的な行動と人間の生活環境とのギャップが生んだ現象です。
アライグマは、食べ物を前足で確認しながら食べる習性があります。触覚が非常に発達しているため、視覚よりも手で触って「安全かどうか」「食べられるかどうか」を確かめようとします。このとき水があると、感触がより正確に伝わるため、水の中で手を動かすのが自然な行動になるのです。
ここで、問題になるのが「わたあめ」という食べ物です。わたあめは見た目こそ大きくふわふわしていますが、水に触れると一瞬で溶けてしまいます。アライグマはそれを知らず、普段通り水で確認しようとした結果、わたあめが消えてしまったのです。これが、動画として大きく注目されることになった背景です。
例えば、ある動画ではアライグマがわたあめを水に入れて、一瞬で溶けてしまったあと、驚いたような様子で辺りを見回すシーンが映されています。この様子が「かわいそうだけどかわいい」「予想外すぎる」とSNSで話題を集め、多くの人の記憶に残る結果となりました。
一方で、このような行動を面白半分で真似することには注意が必要です。動物にとって不自然な食べ物を与えることは、健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。わたあめのような糖分の多い食品は、消化に適していないだけでなく、長期的には肥満や内臓疾患の原因になることもあります。
このように、アライグマがわたあめを洗う行動は、その動物が持つ本能と人間の文化が交差する中で生まれたユニークな出来事です。可愛らしさの裏側にある習性や注意点を知ることで、動物との関わり方にもより深い配慮が必要であることがわかります。
アライグマの目が悪いことと洗う行動の関係

アライグマが「ものを洗うような仕草」を見せる理由については、視覚の弱さが影響しているという見方があります。実際、アライグマの目は決して鋭いわけではなく、特に昼間の視力はそれほど良くありません。彼らの生活スタイルや行動パターンを理解するうえで、この視覚の特徴は重要な手がかりとなります。
アライグマは主に夜行性の動物であり、暗い環境下で活動することが多いです。夜間にエサを探したり、周囲の状況を確認したりするには、視覚だけに頼るのでは不十分な場面も多くあります。このとき重要な役割を果たすのが、非常に発達した「触覚」です。特に前足の感度は非常に高く、細かい凹凸や質感を把握するのに優れています。
このような触覚の鋭さが、アライグマに独特な行動をもたらします。例えば、水辺で前足をまさぐるように動かす仕草は、まるで「洗っている」ように見えますが、実際には物の形や安全性を確かめるための行動です。水の中では、触った物の質感がより分かりやすくなるため、アライグマにとって水は「感覚を強化する手段」として機能しているのです。
たとえば、川辺でエサを探すとき、アライグマは視覚ではなく手で感じながら小魚や甲殻類を見つけ出します。これは、人間にとっての「見て確認する」行動に相当するものであり、アライグマにとっての「手で感じる」は、生きるために欠かせない手段です。
一方で、すべてのアライグマが極端に目が悪いというわけではなく、暗闇に適した視覚は持っています。しかし、細かいものを見分ける力には限界があるため、触覚に頼る行動が顕著に現れるのです。結果として、それが「洗っているように見える」仕草につながっているといえるでしょう。
このように考えると、アライグマの目の性能と洗う行動との関係は、単なる可愛らしい仕草の裏にある、自然界での生き残り戦略であることがわかります。見た目に惑わされず、その本質に注目することが、アライグマの生態を正しく理解する第一歩になります。
アライグマの名前の由来と“洗う”の関係性
「アライグマ」という名前は、日本語で「洗う熊」と書きます。この名前の由来には、彼らが見せる特有の行動が深く関係しています。つまり、ものを前足でこするような仕草が、まるで手を洗っているように見えたことから、そう名付けられたと考えられています。
この命名の背景には、人間の視点が強く反映されています。野生動物の行動を擬人化して理解しようとするのは珍しいことではなく、アライグマもその例外ではありません。実際に、彼らが水辺で前足を動かしている様子は、初めて見る人にとっては「手洗い」としか思えないほど人間的に映ります。
しかし、この行動はあくまで彼らの生態に基づいた本能的なものです。先に述べたように、アライグマは前足の感覚が非常に鋭く、それを使って食べ物を確認したり、周囲の物を探ったりしています。水の中でこの動きを行うことで、触覚の情報がより明瞭になるため、自然と「洗うような仕草」が多く見られるのです。
ちなみに、英語ではアライグマのことを「raccoon(ラクーン)」と呼びますが、これは語源的に「手ですくい取るもの」といった意味を持つネイティブ・アメリカンの言葉に由来しています。つまり、海外でもアライグマの「手の使い方」に注目が集まっていたことがうかがえます。ただし、「洗う」という意味合いまでは含まれていません。
このように、日本語の「アライグマ」という名前は、彼らの行動を視覚的に捉えたうえで名付けられたものであり、文化的な感覚が色濃く反映されています。名前としては非常に的を射ていますが、実際には「洗っている」という意図は本人にはありません。
動物の名前には、その生態や特徴を象徴する要素が多く含まれます。アライグマの場合は、「洗うような行動」が特に印象的だったため、それが名前に反映されたと考えると納得がいきます。このような背景を知ることで、言葉と動物の関係性に対する理解も深まるのではないでしょうか。
アライグマはなぜ洗う?日本での影響と対策を解説

- アライグマ なぜ日本に?外来種としての背景
- アライグマ 被害と人間への影響
- アライグマ 嫌がる匂い・嫌がるものとは?
- アライグマ どこにいる?生息地と遭遇リスク
- アライグマ 出産・繁殖と増加の問題点
- アライグマの肉は臭い?食文化や駆除の実態
アライグマはなぜ日本に?外来種としての背景
アライグマはもともと北アメリカを原産とする動物で、日本の在来種ではありません。それにもかかわらず、現在では北海道から九州まで各地でその姿が確認されており、一部の地域では定着し繁殖まで進んでいます。では、なぜアライグマが日本にやって来たのでしょうか。
その背景には、1970年代に放送された人気アニメ「ラスカル」が深く関係しています。この作品はアライグマをペットとして飼う少年の物語で、多くの視聴者に感動と愛着を与えました。この影響により、当時の日本ではアライグマをペットとして輸入する動きが急増しました。実際、1980年代前半には数千頭単位でアメリカからアライグマが輸入されていた記録があります。
ところが、現実にはアライグマの飼育は決して簡単ではありません。幼いうちは従順で可愛らしく見えるものの、成長するにつれて力が強くなり、気性も荒くなる傾向があります。また、家具を破壊したり、人に噛みついたりといった行動が見られるようになるため、多くの飼い主が手に負えなくなってしまいました。その結果、「かわいそうだから」「山なら生きられるだろう」といった理由で自然に放すケースが相次いだのです。
このようにして放たれたアライグマたちは、日本の自然環境にも比較的容易に適応しました。雑食性で食べ物に困らず、樹上でも地上でも生活できるため、生態系の隙間にうまく入り込んだのです。そして、繁殖力も高いため、徐々に個体数が増加し、野生化が進みました。
この問題に対しては、すでに外来生物法に基づきアライグマは「特定外来生物」に指定されており、輸入・飼育・譲渡が法律で禁止されています。しかし、いったん定着してしまったアライグマを完全に駆除するのは難しく、現在も自治体ごとに対応が分かれているのが現状です。
こうした背景から、アライグマが日本にいる理由は単なる自然の流れではなく、人間の意図と行動の結果として生じたものだといえます。アニメやペットブームといった一時的な流行が、予想以上の影響をもたらす例として、アライグマの外来化は非常に示唆に富んだケースといえるでしょう。
アライグマの被害と人間への影響
アライグマが日本で野生化し始めたことにより、様々な被害が発生しています。外見のかわいらしさとは裏腹に、彼らが及ぼす影響は決して軽視できるものではありません。とくに農業・住宅・生態系に対する被害は深刻で、多くの自治体がその対策に追われています。
まず農業への被害についてですが、アライグマは非常に器用な前足を使って、果物や野菜を食い荒らすことがあります。特にトウモロコシ、スイカ、ブドウ、サクランボなど甘い作物を好む傾向があり、収穫期に畑へ侵入されると、短期間で甚大な損失が出るケースもあります。しかも、彼らは一部をかじって残すことも多く、商品価値を落とす「食害」が問題視されています。
次に、人家への侵入被害です。アライグマは建物の屋根裏や床下に入り込み、そこで巣を作ることがあります。これにより、糞尿による悪臭や建物の劣化が進行するほか、天井裏に住み着いたことで騒音被害が発生することも珍しくありません。さらに、アライグマは鋭い爪で壁や屋根材を破ることもあるため、修繕費用の負担が大きくなる場合もあります。
加えて、感染症のリスクも無視できません。アライグマは「アライグマ回虫」という寄生虫を持っていることがあり、これが人間に感染すると重篤な健康被害を引き起こす可能性があります。特に、小さな子どもやペットが屋外で糞に触れてしまうリスクを考えると、衛生面でも警戒が必要です。
また、自然環境への影響も見逃せません。アライグマは雑食で、鳥の卵やカエル、小型哺乳類なども捕食します。そのため、在来種の個体数が減少したり、生態系のバランスが崩れたりする恐れがあります。特に、希少な生物が生息する地域では、アライグマの存在が生物多様性の脅威となっているのです。
このように、アライグマがもたらす被害は多岐にわたります。外来種問題の一例として、感情的な「かわいい」だけでは語れない現実がそこにはあります。地域社会全体で情報を共有し、早期発見と対応策を徹底することが、被害を最小限に抑えるための第一歩です。
アライグマが嫌がる匂い・嫌がるものとは?

アライグマは非常に賢く順応性の高い動物ですが、苦手とする匂いや物も存在します。人間の生活圏に出没することが増えている今、こうした「嫌がるもの」を知っておくことは、被害予防や対策に役立ちます。
まず、アライグマが嫌がる匂いとしてよく知られているのが、刺激の強いにおいです。たとえば、唐辛子、ハッカ油、酢、アンモニアなどが挙げられます。これらの匂いはアライグマの敏感な嗅覚にとって強すぎる刺激となり、近づくのをためらわせる効果があります。市販の動物忌避剤にも、このような成分を含んだものが多くあります。特に唐辛子成分(カプサイシン)は野生動物の忌避剤として幅広く利用されています。
次に、アライグマが警戒する物としては、光や音の刺激が効果的とされます。夜行性のため強い光を嫌う傾向があり、センサーライトや点滅するLEDライトを設置することで、敷地への侵入を防ぐ対策になります。また、人間の声やラジオの音を流すといった方法も、一定の抑止効果があるとされています。ただし、これらは慣れてしまう可能性もあるため、定期的に種類や場所を変える工夫が必要です。
また、アライグマは特定の材質や地面の状態を嫌がることもあります。例えば、砂利やワイヤーメッシュの上を歩くのを好まない傾向があり、通路などに設置することで侵入を防ぐケースもあります。
ただし、どの方法も100%の効果を保証するものではありません。アライグマは非常に学習能力が高いため、ある対策に慣れてしまえば効果が薄れてしまう可能性もあります。そのため、いくつかの対策を組み合わせて使用することが推奨されます。
最後に、これらの対策を講じる前に重要なのは、アライグマを引き寄せてしまう原因を取り除くことです。ゴミを外に放置したままにしない、収穫前の作物をこまめに管理するなど、基本的な予防策をしっかり行うことで、そもそもアライグマが寄りつかない環境をつくることができます。嫌がる匂いやものを上手に使いながら、日常生活の中でリスクを減らす取り組みが求められます。
アライグマはどこにいる?生息地と遭遇リスク
アライグマは日本に定着した外来種の中でも、特に全国的な広がりを見せている動物の一つです。北海道から九州まで、すでに多くの都道府県で定着が確認されており、都市部とその周辺にまで生息範囲を拡大しています。
本来は森林や河川沿いといった自然環境を好む動物ですが、近年では人間の生活環境にも適応し、住宅地や農地、公園、さらには街中でもその姿が確認されるようになっています。これは、アライグマが非常に柔軟な生態を持っているためで、食べ物がある場所や安全な隠れ家があれば、環境を問わず生活できてしまうからです。
例えば、民家の屋根裏や倉庫、車庫の隙間なども彼らにとっては十分な住処になります。また、ゴミ捨て場や畑、果樹園といった場所は食料の宝庫となり、夜になると頻繁に現れては荒らしていくこともあります。特に、果実の収穫期や生ゴミの多い時期は、アライグマが出没しやすくなるタイミングです。
一方で、農村部や山林だけでなく、都市部でも目撃例が増えてきているのが現在の特徴です。たとえば、東京や大阪といった大都市圏でも、公園や用水路などを通じて移動しながら生息範囲を広げていると報告されています。これにより、野生動物と無縁だと思われていた地域でも、アライグマとの遭遇リスクが高まっています。
さらに注意すべき点として、アライグマは夜行性であるため、日中には見かける機会が少なくても、実際には私たちのすぐ近くで活動している可能性があります。屋根裏で足音がする、ゴミが頻繁に荒らされる、果物がかじられているといった兆候があれば、すでに近くにアライグマが住み着いていることも考えられます。
このような状況を踏まえると、アライグマの生息地は「自然」だけに限らず、「人間の生活圏そのもの」にまで広がっていると考えるべきでしょう。遭遇リスクを下げるためには、日頃からゴミの管理や家屋の点検を行い、被害が広がる前に早めの対応を取ることが重要です。また、地域の野生動物対策情報を確認し、目撃情報があるエリアでは特に注意が必要になります。
アライグマの出産・繁殖と増加の問題点

アライグマが日本各地で増えている背景には、繁殖力の強さと適応能力の高さがあります。この2つの要素が組み合わさることで、外来種としての脅威が年々深刻になっています。特に、出産と繁殖の特徴を理解することで、なぜこれほど急速に個体数が増えているのかが見えてきます。
アライグマは年に1回、春先(おおむね3月から5月頃)に出産期を迎えます。妊娠期間は約2か月と比較的短く、一度の出産で4~6頭の子どもを産むことが一般的です。この子どもたちは生後数か月で自力で行動できるようになり、翌年にはすでに繁殖が可能な個体へと成長します。このように、世代交代のサイクルが早く、少ないペースであっても確実に個体数が増加していきます。
また、アライグマは非常に順応性が高く、人間の生活圏にも素早く適応します。例えば、屋根裏や倉庫の隙間などを巣作りに利用することで、天敵の少ない都市部でも安全に出産・子育てを行えるのです。これにより、農村地帯だけでなく住宅街でも繁殖が進み、予想以上のスピードで分布を広げています。
この増加傾向には、いくつかの問題点が伴います。まず第一に、生態系への悪影響です。アライグマは雑食性で、鳥の卵やカエル、小動物なども捕食するため、在来種の生息を脅かす存在となっています。とくに、すでに個体数が少ない希少種にとっては深刻な脅威となりかねません。
さらに、個体数が増えることで人間との接触機会も増えます。農作物の被害や建物への侵入、感染症のリスクなど、生活への影響が現実的なものとなってきています。一部の自治体では捕獲や駆除の対策が取られているものの、出産ペースに追いつかないというのが実情です。
このように、アライグマの出産と繁殖は極めて効率的であり、その結果として日本国内での定着・増加が深刻な問題となっています。今後は生息域の監視や対策の強化、さらには根本的な外来種管理の在り方について、地域全体で考えていく必要があるといえるでしょう。
アライグマの肉は臭い?食文化や駆除の実態
アライグマは可愛らしい見た目とは裏腹に、害獣としての一面も持っています。国内では主に駆除対象として扱われていますが、海外では一部の地域でアライグマの肉が食用とされていることがあります。こうした話を聞いたときに、多くの人が気になるのが「アライグマの肉は臭いのか?」という点です。
実際、アライグマの肉は一般的に臭みが強いとされています。これは、野生動物特有の脂肪の質や、日常的に食べているものが関係しています。雑食性のアライグマは、木の実から昆虫、時にはゴミに至るまで様々なものを食べます。このような食生活が肉質に影響し、調理しても独特の獣臭が残りやすいのです。
そのため、食用にする際には下処理が非常に重要です。アメリカ南部などでアライグマを食べる文化がある地域では、肉を酢や香草で漬け込んで臭みを和らげたうえで煮込み料理やスモークにするのが一般的です。ただし、これはあくまで一部の伝統的な食文化であり、日本においてはアライグマの肉を食べることはほとんどありません。
一方で、日本国内ではアライグマは特定外来生物に指定されており、飼育や譲渡、輸入が法律で制限されています。駆除の対象となることも多く、農林水産業への被害や生態系への悪影響を減らすため、自治体による捕獲や罠の設置が行われています。捕獲されたアライグマは、原則としてその場で処理されるか、専門機関に引き取られる形となります。
ちなみに、捕獲後のアライグマを食用に回すという考えは、日本では実用的ではありません。衛生管理の問題に加え、回虫などの寄生虫が人体に悪影響を及ぼすリスクもあるため、食用とするには厳重な処理が必要です。加えて、多くの人がアライグマに「可愛い」というイメージを持っているため、倫理的な抵抗感を覚える方も多いでしょう。
このように、アライグマの肉が食用になるかどうかという点については、文化的背景や衛生面、倫理観など複数の要素が関わっています。日本では実際に口にする機会はほとんどありませんが、その扱われ方を知ることで、駆除の現場や野生動物に対する理解が深まるかもしれません。
アライグマはなぜ洗うのか?行動の理由と影響をまとめて解説

- アライグマの前足には多くの神経が集中しており、視覚よりも触覚で物を確認する特性がある
- 水の中では感触がより鮮明になるため、手をこすり合わせて食べ物の状態を確かめる行動が目立つ
- まるで洗っているような動きは、獲物を確認するための本能的な行動にすぎない
- 飼育されているアライグマでも同様の行動が見られ、本能としてこの動作が強く残っている
- 昼間の視力はあまり良くなく、特に夜間や暗所では触覚への依存度がさらに高まる
- 実際には水がなくても同じ動きをすることがあり、洗浄や衛生とは無関係である
- アライグマが「手を洗っている」と感じるのは、人間の感覚による誤解に基づいた見方である
- 日本語の「アライグマ」という名前は、洗っているように見える仕草から付けられたものである
- 一方で英語の「raccoon」の語源は「手ですくうもの」であり、洗う意味は含まれていない
- わたあめを水に入れて溶かしてしまう動画は、本能的行動と人間の文化が交錯した象徴的な例である
- 手を動かす仕草が人間的で愛らしく見えることから、SNSや動画で人気を集めている
- 元は北アメリカ原産の外来種であり、日本にはペット目的で輸入された経緯がある
- アライグマは繁殖力が高く、年1回の出産で複数頭を産むため野生化後の個体数増加が早い
- 果樹や野菜への食害、家屋への侵入被害が報告されており、農業・生活への影響が深刻化している
- 強い匂い(唐辛子、酢など)や光、音への警戒心があり、それらを使った対策が一定の効果を持つ
関連記事



コメント