「マーモット 日本で飼える 人懐っこい」と検索してたどり着いたあなたは、きっとマーモットという動物に興味を持ち、「ペットとして飼えるのか」「どんな性格なのか」「日本で会える場所はあるのか」といった疑問をお持ちなのではないでしょうか。
マーモットは、その丸くてふわふわとした見た目や、少しとぼけたような仕草が魅力の動物です。人に慣れることもあるため、海外ではペットとして人気を集めています。しかし、日本では流通が限られており、飼育に関する情報も少なく、ハードルの高い動物のひとつです。
この記事では、「マーモットは日本で飼えるのか?」という根本的な疑問から始まり、法律や飼育の現実、性格、匂いやしつけの問題、見られる場所や価格情報にいたるまで、幅広く丁寧に解説しています。マーモットと暮らすことを真剣に考えている方も、ただ可愛さに惹かれて興味を持った方も、この記事を読むことで正しい知識と判断材料を得られるはずです。
マーモットとの暮らしがどんなものなのか、ぜひ最後まで読んで確かめてみてください。きっとあなたの中にある「本当に飼えるのか」「会いに行けるのか」というモヤモヤが、少しずつ晴れていくことでしょう。
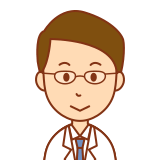
💡記事のポイント
- マーモットが日本で合法的に飼育できるかどうか
- 飼育に必要な手続きや費用の目安
- マーモットの性格や人への慣れやすさ
- 日本でマーモットに会える場所や展示施設
マーモットは日本で飼える?飼育の可否と注意点を徹底解説

- マーモットはペットとして飼える?法規制と許可の現状
- マーモットのペットの値段はいくらですか?入手可能性と相場
- マーモットは日本で飼える?輸入や飼育の現実
- マーモットとモルモットの違いとは?似てる動物との比較
- マーモットは匂いがしますか?飼育環境と衛生管理のポイント
- マーモットは噛む?性格やトラブル防止のしつけ方法
マーモットはペットとして飼える?法規制と許可の現状
マーモットは一見モルモットにも似た、愛らしくて人懐っこい印象を持つ動物ですが、日本でペットとして飼えるかどうかは慎重に確認する必要があります。というのも、マーモットは野生動物として分類されており、その取り扱いには法律上の制限があるためです。
まず、日本では「外来生物法」や「動物の愛護及び管理に関する法律」などに基づき、輸入・飼育が制限される動物がリスト化されています。マーモットの一部種は、感染症の媒介や生態系への影響の可能性があるとして、特定外来生物や検疫対象動物に指定されることがあります。その場合、許可なしに輸入や飼育を行うことはできません。
このため、もしマーモットをペットとして飼いたいと考えるのであれば、まず最寄りの自治体や環境省、または動物検疫所に確認をとることが必須です。飼育の可否は時期や対象種によっても変動するため、「以前は飼えた」という情報が現在も有効とは限りません。
また、マーモットは農業被害や感染症対策の観点から、輸入規制が厳しくなっている背景もあります。特に過去には、一部の種類の輸入が中止されたケースもあり、「日本撤退」という表現でニュースになったこともあります。これには、取引量の低下や輸入コストの上昇といった複数の要因が関係しています。
いずれにしても、マーモットを安易にペットとして迎えるのはリスクが高く、信頼できる情報源をもとに判断することが求められます。無許可での飼育が発覚した場合、罰則が科される可能性もあるため、慎重に調査した上で行動することが大切です。
マーモットのペットの値段はいくらですか?入手可能性と相場
マーモットをペットとして飼おうと考えたとき、まず気になるのが価格ではないでしょうか。実際、マーモットは一般的なペットショップではほとんど取り扱われていないため、値段や入手手段に関する情報が少なく、不透明に感じる方も多いと思います。
このような状況の背景には、マーモットが特定の国や地域に生息する野生動物であること、また日本国内での流通が非常に限定的であることが関係しています。結果として、マーモットを購入できるルートはほぼ輸入業者やエキゾチックアニマル専門のブリーダーに限られます。
相場としては、マーモット1匹あたりおおよそ20万円〜40万円程度になることが多く、種別や健康状態、輸送方法によって価格に大きな差が出ます。さらに、輸入に伴う諸経費や検疫、許可申請などの手続きも必要になり、それらの費用を含めると最終的なコストは50万円近くになる場合もあります。
例えば、ヨーロッパや北米からの輸入が主流であるため、飛行機による輸送や検疫施設での一時的な飼育コストなども加算される点に注意が必要です。また、入手時期や為替レートの影響も無視できません。これらの条件が重なることで、同じ種類でも時期によって値段が大きく変動します。
さらに重要なのは、マーモットはそもそも流通量が非常に少なく、常に販売されているわけではないという点です。専門の業者でも予約制となっていたり、年に数回しか入荷がない場合も多いため、タイミングと事前準備が非常に重要になります。
このように考えると、マーモットを飼うには単に費用だけでなく、入手ルートの確保や法的な確認もセットで行わなければなりません。興味本位で飼うにはハードルが高く、責任ある姿勢が求められるペットだと言えるでしょう。
マーモットは日本で飼える?輸入や飼育の現実
マーモットを日本で飼うことは、現実的には非常に難しいとされています。インターネット上には「マーモットをペットにしたい」といった声も見られますが、実際のところ、日本国内でマーモットを合法的に入手し、一般家庭で飼育するには多くのハードルがあります。
まず、日本ではマーモットは「野生動物」に分類され、ペットとして一般流通していません。この分類は、飼育による感染症リスクや生態系への影響を考慮したものです。そのため、環境省や動物検疫所が定めた手続きなしでの輸入・飼育はできません。具体的には、検疫の申請や輸入許可が必要となり、一般の個人が独自にマーモットを海外から取り寄せることは、現実的ではありません。
さらに、マーモットは自然環境に適応している生き物であり、日本の室内飼育に向いているとは言いにくい一面もあります。寒冷な高山地帯を生息地としているため、高温多湿な日本の気候はマーモットにとってストレスとなることがあるのです。こうした点からも、専門的な知識や設備がない状態での飼育はおすすめできません。
もう一つの課題として挙げられるのが、国内のブリーダーや専門業者がほとんど存在しないという点です。一部のエキゾチックアニマル専門業者で輸入実績がある場合もありますが、その取り扱いは非常に限定的であり、常に入手できるとは限りません。加えて、輸入動物はすべて検疫対象となるため、感染症の有無を確認するための隔離措置や検査期間が発生します。これにより、実際に手元に届くまでに数ヶ月かかるケースもあります。
このような状況を考慮すると、マーモットを日本で飼うことは可能性がゼロではないものの、専門業者との密な連携や法的手続き、飼育環境の整備が欠かせません。興味本位で飼おうとするにはリスクが高く、動物と暮らす責任を十分に理解した上で慎重に判断することが必要です。
マーモットとモルモットの違いとは?似てる動物との比較

マーモットとモルモットは名前も見た目も似ているため、混同されることが少なくありません。しかし、この2種は分類や生態、飼育しやすさにおいて明確な違いがあります。ここでは、その違いをわかりやすく整理して解説します。
まず分類上、マーモットはリス科に属する動物で、北米やヨーロッパの山岳地帯などに野生で生息しています。一方、モルモットはテンジクネズミ科に分類されており、南アメリカ原産の小型哺乳類です。このように、見た目の雰囲気は似ていても、遺伝的にはまったく異なる系統の動物です。
次に体の大きさについてですが、モルモットは体長20〜30cm程度で、家庭用の小動物ケージでも飼育可能なサイズです。一方、マーモットは種類によって差はありますが、体長50cmを超えることもあり、かなりのスペースを必要とします。さらに、マーモットは季節によって冬眠する習性がありますが、モルモットには冬眠の習性がありません。この点は、飼育スタイルにも大きく影響する部分です。
また、性格面でも違いがあります。モルモットは比較的おとなしく、飼い主に慣れやすいため、ペットとして古くから親しまれています。多くのモルモットは臆病ながらも扱いやすく、小学生の飼育体験に利用されることもあります。これに対してマーモットは、野生に近い行動を見せることが多く、なつくまでに時間がかかる傾向があります。ストレスに弱い一面もあり、無理な接触を避ける必要があります。
このように考えると、モルモットは初心者向けの飼いやすい小動物であるのに対し、マーモットは飼育に高度な知識と環境が求められる動物だと言えるでしょう。見た目の可愛らしさに惹かれてどちらかを選ぼうとする場合も、こうした生態や習性の違いをしっかりと理解しておくことが大切です。
マーモットは匂いがしますか?飼育環境と衛生管理のポイント
マーモットを飼いたいと考える人の中には、「匂いは気にならないのか?」と不安に思う方も多いかもしれません。実際、動物の種類によっては体臭や排せつ物の匂いが強く、室内飼育においてトラブルの原因となることがあります。
マーモットの場合、野生下では主に山岳地帯などの涼しい環境で生活しており、汗腺も少ないため、体そのものから強い体臭を発することはあまりありません。ただし、飼育環境によっては匂いが発生しやすくなる場合があります。特に排せつ物を放置したり、巣材が湿気を含んだままになっていると、アンモニア臭やカビ臭が強くなることがあります。
このため、衛生管理は非常に重要です。まず、ケージは風通しの良い場所に設置し、週に1〜2回はしっかり掃除を行うことが基本です。床材として使用する牧草やおがくずなどは、湿気を吸収しやすいため、こまめに取り替えるようにしましょう。また、水の容器が倒れてケージ内が濡れることがないよう、給水器のタイプにも気を配る必要があります。
さらに、夏場の高温多湿な環境では匂いの発生が特に顕著になるため、エアコンや除湿器で湿度管理を行うのも効果的です。空気の循環が悪い場所にケージを置いてしまうと、匂いが部屋全体に広がりやすくなります。換気や空気清浄機の併用もおすすめです。
もう一つ見落とされがちなのが、マーモット自身の毛づくろいや分泌物による匂いです。定期的にブラッシングを行い、毛に付着したゴミや皮脂を取り除くことで、清潔な状態を保つことができます。ただし、シャンプーなどの洗浄行為はストレスになるため、基本的には避けた方が良いでしょう。
このように、マーモット自体は強い匂いを持っていないものの、飼育環境によって匂いの感じ方が大きく変わってきます。快適に共生するためには、衛生的な飼育空間を維持する日々の工夫が不可欠です。
マーモットは噛む?性格やトラブル防止のしつけ方法
マーモットに対して「見た目はかわいいけど、噛まれたりしないの?」という不安を抱く人は少なくありません。確かに、動物の中には緊張や恐怖を感じた際に防衛本能から噛みつく習性を持つものも多く、マーモットも例外ではありません。
まず知っておきたいのは、マーモットは本来、臆病で警戒心の強い動物だということです。野生では外敵から身を守るために穴を掘って生活しており、驚かされたり、無理に触れられたりすると、防御反応として噛みつくことがあります。これは攻撃というより、自己防衛に近い行動です。
このため、人間との関係性を築くには「慣らす」プロセスが非常に重要になります。いきなり抱っこしたり、急に手を差し出したりするのではなく、まずはマーモットが自ら近づいてくるのを待つ姿勢が求められます。餌を手渡すといった方法で徐々に信頼を築くと、警戒心が和らぎ、穏やかに接してくれるようになるケースが多いです。
しつけの面では、噛まれた際に大きな声を出して驚かせてしまうと、かえって恐怖心を植え付けてしまうことがあります。もし噛まれてしまった場合は、冷静に手を引き、過度な反応を示さないようにすることがポイントです。そして、どのような状況で噛んだのかを観察し、その原因を避けることが最も効果的な対策になります。
また、マーモットには個体差があり、比較的おとなしい性格の子もいれば、警戒心が強くなかなか慣れない子もいます。性格に合わせた接し方を心がけることが、トラブルを防ぐ一番の方法です。必要に応じて、エキゾチックアニマルに詳しい獣医師や専門家に相談するのもよいでしょう。
このように、マーモットが噛むかどうかは、その動物の性格や環境、接し方によって大きく左右されます。適切な距離感と丁寧な慣らしを通して、安心して暮らせる関係を築くことが大切です。
マーモットは日本で飼える?人懐っこい性格・習性・会える場所を紹介

- マーモットはなつく?人との関係性と慣れやすさ
- マーモットの性格は?面白い行動や喧嘩の理由
- マーモットはどこにいる?野生分布と日本で見られる場所
- マーモットは日本で会える?動物園や施設の最新情報
- マーモット 日本撤退の理由とは?過去の輸入状況と変遷
- マーモットの体長・特徴は?見た目の魅力と可愛さの秘密
マーモットはなつく?人との関係性と慣れやすさ
マーモットは見た目の愛らしさから、「人に懐いてくれるのか」「触れ合える動物なのか」と気になる方も多いと思います。実際、マーモットは適切な接し方と環境さえ整っていれば、人との信頼関係を築くことができる動物です。ただし、そのプロセスには時間と根気が必要になります。
まず、マーモットは野生では警戒心の強い性格を持っており、危険を感じたときには素早く巣穴に隠れたり、鋭い警戒音を発したりする習性があります。この性質があるため、初対面の人間に対してすぐに懐くというタイプではありません。特に、音や動きに敏感であるため、いきなり抱き上げるような行動は避けた方がよいでしょう。
こうした前提をふまえたうえで、マーモットとの距離を縮めるには「慣れるまでそっと見守る姿勢」が重要です。例えば、餌を手のひらから与えるところから始め、徐々にマーモットが人の存在に安心感を持てるように工夫することが有効です。静かな環境で規則正しく接することで、徐々に警戒心が薄れていきます。
なついたマーモットは、飼い主のそばに寄ってきたり、鳴き声や仕草で甘えるような行動を見せることもあります。ただし、モルモットやウサギのような「人なつっこさ」を期待しすぎるのは禁物です。マーモットは独立心の強い一面も持っており、気ままに過ごすのを好む傾向があります。
このように、マーモットは「なつく」というより、「人に慣れる」と表現するほうが適しているかもしれません。無理に距離を詰めようとせず、相手のペースに合わせることで、穏やかな関係性を築くことができるでしょう。
マーモットの性格は?面白い行動や喧嘩の理由
マーモットの性格は、一言で言えば「繊細で賢く、社会性のある動物」といえるでしょう。外見からはあまり想像がつかないかもしれませんが、マーモットは群れで生活することが多く、仲間との関係性を大切にする動物です。そのため、観察しているとさまざまな面白い行動を見ることができます。
たとえば、マーモットは日光浴をする習性があり、岩の上に腹ばいになって日なたぼっこをする様子はとてもユーモラスです。また、鳴き声を使ったコミュニケーションも活発で、危険を知らせるときには高い警戒音を発し、仲間と情報を共有する行動も見られます。こうした行動は見ていて飽きることがなく、飼育している人にとっては大きな魅力の一つになるでしょう。
一方で、同じ空間で複数のマーモットを飼っていると、時折喧嘩をすることがあります。これは単なる仲間割れというより、縄張り意識や順位づけによるものであることが多いです。特にオス同士では、繁殖期やエサの取り合いをきっかけに争いが起こるケースがあります。喧嘩の際は鳴き声を上げたり、体をぶつけ合ったりする行動が見られますが、怪我に発展することもあるため、放っておくのは危険です。
このような状況を防ぐためには、ケージの広さを確保したり、エサの配置を工夫するなど、ストレスの原因を取り除くことが大切です。また、単独飼育を選ぶのも一つの方法です。マーモットは社会性があるとはいえ、すべての個体が他のマーモットとの共存に向いているわけではありません。
このように、マーモットの性格は一見おとなしいようでいて、実は豊かな感情と行動パターンを持つ動物です。興味深い仕草に惹かれる一方で、適切な飼育環境と理解が求められます。日々の観察から性格を読み取り、ストレスの少ない環境を整えてあげることが、より良い関係性を築く鍵となります。
マーモットはどこにいる?野生分布と日本で見られる場所
マーモットは、リス科に属する大型の齧歯類で、世界各地の山岳地帯や草原に生息しています。日本国内では野生のマーモットは見られませんが、動物園などで飼育されている個体を観察することができます。
まず、マーモットの野生分布について見ていきましょう。マーモットは、主にヨーロッパ、アジア、北アメリカの高山地帯や草原に生息しています。例えば、ヨーロッパではアルプス山脈やピレネー山脈、アジアではヒマラヤ山脈やシベリアの草原地帯、北アメリカではロッキー山脈やシエラネバダ山脈などが主な生息地です。これらの地域は、冷涼な気候と開けた地形が特徴であり、マーモットが巣穴を掘って生活するのに適した環境となっています。
一方、日本国内には野生のマーモットは生息していません。そのため、自然の中でマーモットを観察することはできませんが、動物園やアニマルカフェなどで飼育されている個体を見ることが可能です。これについては、次の見出しで詳しくご紹介します。
マーモットは日本で会える?動物園や施設の最新情報

日本国内でマーモットに会いたい場合、いくつかの動物園やアニマルカフェで飼育されている個体を観察することができます。以下に、2025年現在、マーモットを展示している主な施設をご紹介します。
1. 伊豆シャボテン動物公園(静岡県伊東市)
この動物園では、ボバクマーモットが飼育されています。ボバクマーモットは、中央アジアの草原地帯に生息するマーモットの一種で、比較的人懐っこい性格が特徴です。伊豆シャボテン動物公園では、マーモットの他にも多種多様な動物や植物を楽しむことができます。
2. 那須どうぶつ王国(栃木県那須町)
こちらの施設では、ウッドチャックと呼ばれるマーモットの一種が飼育されています。ウッドチャックは、北アメリカ原産で、地面に巣穴を掘って生活する習性があります。那須どうぶつ王国では、動物たちとのふれあい体験も充実しており、家族連れにも人気のスポットです。
3. アニマルリゾートNOAH(千葉県)
この施設では、ボバクマーモットが飼育されています。アニマルリゾートNOAHは、動物たちと間近で触れ合えることをコンセプトにした施設で、マーモットの他にも様々な動物たちと交流することができます。
4. マーモット村(東京都中野区)
2025年5月にオープンした、マーモット専門のアニマルカフェです。ここでは、日本で唯一、ヒマラヤマーモットを間近で観察することができます。ヒマラヤマーモットは、その愛らしい外見と人懐っこい性格から、近年注目を集めているマーモットの一種です。マーモット村では、事前予約制で、マーモットとのふれあいや餌やり体験が楽しめます。
これらの施設では、マーモットの生態や行動を間近で観察することができ、マーモットに興味を持つ方にとって貴重な体験となるでしょう。訪問の際は、各施設の公式ウェブサイトなどで最新の情報を確認し、事前予約や注意事項を把握しておくことをおすすめします。
マーモット 日本撤退の理由とは?過去の輸入状況と変遷
マーモットはそのユーモラスな見た目や温厚な性格から、一部の動物好きに人気のある存在ですが、日本国内でその姿を見る機会は年々減少しています。過去には、輸入によって限られたルートでペットや展示動物として扱われていたマーモットが、現在ではほとんど流通していない背景にはいくつかの要因が存在します。
かつては、エキゾチックアニマルのブームや海外との取引自由化に伴い、ボバクマーモットなどがヨーロッパや中央アジアから日本に輸入されていました。一部の動物園や専門業者では繁殖個体も見られ、マニアの間では密かに人気を博していた動物の一つです。しかし、その流れは徐々に縮小していきました。
最も大きな転機となったのは、国際的な感染症対策や生態系保護に関する法規制の強化です。マーモットはプレーリードッグやリスと同様に、齧歯類としてペストなどの感染症を媒介するリスクがあるとされ、輸入には厳しい検疫や許可が求められるようになりました。2000年代後半には、特定地域からの輸入が実質停止となり、取り扱う業者も減少しています。
また、輸送コストや飼育管理の難しさも、日本でのマーモット流通にブレーキをかけました。マーモットは温度や湿度に敏感な動物であり、日本の気候は本来の生息環境とは大きく異なります。こうした条件下で健康を維持するには、高度な飼育スキルや設備が必要になるため、一般の愛好家には手が出しにくい存在となっていきました。
このような流れを受け、「マーモットは日本から撤退した」と言われるようになりましたが、正確には流通の停止・縮小であり、完全に絶滅したわけではありません。現在でも一部の動物園や、極めて限定的な業者においては飼育例が見られます。しかし、過去のように市場に出回ることはほとんどなく、今では非常に珍しい存在になってしまったというのが実情です。
マーモットに再び会いたいという方は、展示されている動物園の情報を確認するのが現実的な選択となります。マーモットの日本における輸入・飼育の歴史は、動物との共生のあり方やリスク管理の重要性を再認識させてくれる一例と言えるでしょう。
マーモットの体長・特徴は?見た目の魅力と可愛さの秘密
マーモットと聞くと、「大きなモルモットのような動物?」というイメージを持つ方もいるかもしれません。確かにその姿は小動物のように愛らしく、ぬいぐるみのような見た目が特徴です。しかし、実際の体の大きさや特徴を知ると、その印象は良い意味で裏切られるでしょう。
まず、マーモットの体長は種類によって異なりますが、一般的には40〜60cmほどまで成長します。大きい個体になると、尾を含めて70cm近くになることもあり、見た目以上にしっかりとした体格をしています。体重は2kgから最大8kg程度まであり、モフモフとした毛並みがより一層その存在感を際立たせています。
特徴的なのは、丸みを帯びた体型と短めの四肢です。これらは、寒冷な高地での生活に適応するための形状であり、巣穴を掘るのに適した太くて丈夫な前足もマーモットの特徴です。また、体毛は季節によって生え変わり、冬には非常に密度の高いふわふわの毛で全身が覆われます。この状態のマーモットは、まさに冬眠前の「丸くて可愛い姿」をしています。
さらに、顔の表情が豊かで、黒く丸い目と短い鼻先が人間の表情に近く感じられることから、愛着を持ちやすい動物です。人によっては、アルパカやカピバラのような癒し系動物と同じカテゴリーで捉えることもあります。実際、ヨーロッパでは山岳地帯でマーモットを見かけると、観光客が写真を撮ろうと群がるほどの人気ぶりです。
このように、マーモットの可愛さは単なる外見だけではなく、「自然に適応した体型」「表情のある顔立ち」「柔らかそうな毛並み」といった複数の要素が組み合わさって生まれています。その魅力は一度目にしたら忘れられないインパクトがあり、動物園での人気が高いのも頷ける話です。
もしマーモットに興味を持ったなら、実際に展示されている施設でその姿を観察することをおすすめします。写真では伝わらない、愛らしさと迫力を同時に感じることができるはずです。
マーモットは日本で飼える?人懐っこい性格と飼育事情のまとめ

- 日本でマーモットを飼うには、法律による規制を確認する必要がある
- 飼育を希望する場合は、動物検疫や環境省からの輸入許可が求められる
- 一般的なペットショップでは販売されておらず、流通ルートは非常に限られている
- マーモットを購入できる可能性があるのは、エキゾチックアニマル専門の業者や輸入ブリーダーのみである
- マーモット1匹の販売価格は20万円から40万円が相場で、種類や状態によって異なる
- 検疫や輸送、各種手続き費用を含めると、最終的な購入コストは50万円近くに上ることもある
- 日本の高温多湿な気候は、寒冷地出身のマーモットには適していない環境である
- 気温や湿度の管理が不十分な場合、体調を崩すリスクが高まるため注意が必要
- マーモット自体の体臭は少ないが、飼育環境の清掃が不十分だと匂いが発生しやすくなる
- 警戒心は強いが、人との接触を重ねることで次第に慣れてくる傾向がある
- 威嚇や驚きから噛むことがあるが、しっかりと信頼関係を築けば回避できる
- 野生のマーモットは、主にアルプス山脈やヒマラヤ、ロッキー山脈などの高山地帯に生息している
- 日本の自然環境にはマーモットの生息例がなく、野外で見られることはない
- 伊豆シャボテン公園や那須どうぶつ王国など、一部の動物施設で飼育展示されている
- 過去にはペット目的での輸入もあったが、現在は法規制や感染症対策の影響で取り扱いが大幅に減少している
関連記事



コメント